ボスと白昼夢
まえがき。
このお話は手書きブログで描いていた「無縁坂」を文章に起こしたものです。
漫画はもう完成しないのでは? という予感がしました。しかしそのまま放りだすのはあまりにも無責任、かつ無念……せっかくプロットまで書いたし。という自己満足のためだけに完成させました「無縁坂」改め「ボスと白昼夢」。漫画から小説に形式を変えたため、表現方法の違いという理由でタイトルを変えました。でも同じプロットを使って書いているので内容は同じです。
漫画を読んでいなくても楽しめるよう書きました。どうか一時、楽しんでいただければ幸いです……。

一
数年前の話になるけど、その頃わたしは今まで積み上げたものをすべて捨てて、逃亡生活を送っていた。
なぜそんな生活になってしまったのか。それは不可抗力の結末で、わたしには全く非がないことなので話したくはない。これまでの経験上、誰かに相談するという行為は無意味だ。自分の思うような結果が出た試しはないし、「頑張れ」とか「我慢すればいいの」なんて無責任なことばかり言われて余計に気分が悪くなる。
小さいころから勉強が嫌いではなかったし、頭も悪いほうではなかった。友人もそれなりにいたし、我慢さえすれば食べるものも住む場所もあった。ただ同居人の影響で男のことが大嫌いになっていたから、水商売なんかは死んでもやりたくなかったわけ。彼らのくだらないプライドを満足させるために媚びを売るなんてまっぴらゴメンだった。
でもじゃあ社会がわたしを受け容れてくれるかといえば、けっしてそんなこともなく、身元を保証してくれる唯一の人間から逃げ出したわたしを雇ってくれるような会社なんて、――結局あるわけなかったのだ。
そんな想いを血がにじむほど噛みしめていたとき。わたしはボスと出会った。
"男"という存在に心を開いていなかったからかなり失礼な態度をとっていたけど、ボスはそんなこと微塵も気にせず、「君は頭が良いな」とわたしを褒めてくれた。
ボスはわたしが今までであった男とは違うようだった。
本当はわからないくせに知ったかぶったり、実力もないくせにふんぞり返ったり、自分の自尊心を保つためだけに暴力をふるったり。そういうことをする人間を彼自身も嫌っているようだった。そして見た目や環境で人を判断したりすることも、なかった。
こうしてわたしはボスの元で働くことになった。
まだボスもわたしも、お互いに若かったころの話だ。
二
ギンガ団は新しいエネルギーの研究、開発を主に行っていて、またその合間に偶然できた発明品を売買して利益を得ていた。ボスはまだ若く年齢に似合わないほど会社は大きかった。わたしが入社した時はまだハクタイシティに支所はなかったけど、資本や従業員の人数は、とても最近出来たばかりの会社だとは思えなかった。
だから、何か裏のある会社だと、すぐにわかった。
それに気づく人間はわたし以外にもいたけれど、でもどういうわけか、そういう人はいつの間にかいなくなっていたから、団内はいつも統率のとれた状態を保っていた。
ギンガ団では月に一度、ボスが団員全員の前で演説をするのが恒例行事になっている。
わたしはそれを何よりも心待ちにしていた。
彼が何を考え、今後どのようにして生きていくのか。それを知ることで、わたしは自分の中に"ボス自身"を見出すことができた。自分とボスに共通点を見つけるたびに、わたしはわたしの輪郭を知ることができた。かつての境遇で尊厳を持つことの許されなかったわたしに、ボスはいとも容易くそれを与えてくれた。
何も持たないわたしに、ボスは本当に様々なものを下さった。
わたしがこれ以上何も望めないと想う、それ以上のものをいつも彼はわたしにくれた。
この世に神さまがいるのなら、それは間違いなく彼のことだと思う……。
そういうわけで、会社の裏に利益以外のことを目的とした背景があるように感じながらも、わたしは見てみぬフリをして働いた。元々アンダーグラウンドにいたようなものだから、少しくらい都合の悪いことが起こるかもしれなくったって平気だった。わたしのような人間には、なんとも働きやすい職場だった。
 三
三
入社したころから突然人がいなくなる職場だった。
昨日までいた同僚が出社しなくなって、連絡も取れなくなる。幹部の人に聞いても理由がはっきりしたためしはない。都合が悪くなったのだろう、と幹部は言った。誰の都合なのか、何の都合なのか、そういうことは聞けなかった。聞いてしまったら自分までここにいられなくなる気がした。下っ端の姿が皆一様に同じ理由もその「都合」とやらにあると思った。
「君を幹部に昇進させたい」
社長室に呼び出され、こう言われたときは驚いた。
「以前の方は、どうされたのですか?」
「以前の幹部は都合が悪くなって退社した。代わりを君にお願いしたい」
……いったい誰の都合が悪くなったんだか。
そうは思いながらも、幹部へ昇進という話の魅力には敵わなかった。
ギンガ団に年功序列というものはない。年上だろうが使えない人間は下っ端だし、若くてもボスに認められれば幹部になれる。ボスの傍に、いられるようになるのだ。
「わたしのような人間で勤まりますでしょうか……?」
「君の働きぶりには目を瞠るものがある。私は君が適任だと思うが、引き受けてくれないだろうか」
「……もったいないお言葉、感謝いたします」
「そんなに畏まらなくてもかまわないよ」
ボスは短く笑うと、後のことはサターンから聞いてくれ、と言った。
こうしてわたしは多くの疑問に目をつぶりつつ、幹部に昇進したのであった。
四
次の年にはまだ若かったマーズが幹部に昇進し、それ以降プルートが加わること以外に、幹部の人事に変動はなかった。
この頃になると世界を新しく作るという野望が下っ端たちにも伝わるようになっていて、わたしたちギンガ団は宇宙エネルギーの開発と研究を謳いながら、その裏では世界を作り直そうと目論んでいた。
あるとき珍事が起こる。
マーズがボスに、バレンタインデーのチョコレートをプレゼントしたのだ。
そしてボスがそれを受け取ったと言う。
その話はマーズから嬉しそうに聞かされたのだが、わたしは内心ドギマギしていた。
ボスは俗世のイベントが好きではない。自分の中の価値観を信じていたから誰かに踊らされることが面白くなかったのだろう。だからバレンタインやクリスマスといったイベントは企業の陰謀だからわざわざ実行する必要などないという発言を、よくしていたのだ。
マーズは頭が悪い。故に遠まわしにイベント事を批判していたボスの話もよく理解していなかったのだろう。そんな頭の悪さはボスも理解していて、だからチョコレートを受け取ってあげた……。
(明日になったらマーズ、いなくなっちゃってるんじゃないかしら……)
と、マーズを心配するフリをしながら、本当はマーズをうらやんでいた。これはどうかしていたとしか言いようのない話なのだが、わたしもこの日綺麗に包装されたチョコレートを持ってきていたのだ!
(わたしもボスにチョコをあげれば、ボスはマーズのことも大目に見てくれるかもしれないわね)
わたしは自分自身に言い訳をしていた。そうでもしなければチョコレートなんて、一生かかってもプレゼントできなかったと思う。
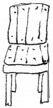
五
わたしはボスにチョコを渡した。そしてボスもそれを受け取ってくれた。
思えばあの時の、わたしたち――マーズをかばったわたしと、わたしたちのチョコを受け取ったボス――の奇妙な同情が、いまのこの状況を生んでしまったのではないだろうか。
わたしたちはバラバラになってしまった。
「どうしてアカギさまの居場所がわからないのよ!」
机を叩き、怒りをあらわにしているマーズは、ここ最近ずっと苛立っている。神経が過敏になっているのだ。五感が通常の反対方向を向いてしまっていてコントロールできていない。報告した下っ端は今にも泣き出してしまいそうだった。
「いったいどういう探し方しているの!?」
「も、もうしわけ……」
「やめろマーズ。部下に当たるな」
サターンが口を挟み、マーズの気がサターンにそれる。
「当たってないわよ、本当のことを言ってるだけでしょ?」
「それがいけないと言っているんだ」
「心配するのがいけないっていうの?」
「そうやって食って掛かるなと言っている」
二人が言い争っているうちに、「もういいから行きなさい」と部下を逃がした。部下はおびえながらも足早に逃げていった。わたしたちはバラバラになってしまった。
こんな結末を、誰が望んだだろう。
二人の互いに主張を譲らない様子を、なんとも言えない気持ちで見つめていた。どうしてこんな事になってしまったんだろう。わたしたちは純粋にボスのことを慕っていた。お金を稼ぐのが上手かったからじゃない。人を使うことが上手かったからでもない。わたしたちはボスを通して夢を見ていた。それがそんなにいけないことだったのだろうか? 自分たちを大切にしてくれなかった世界なんて愛さなくてもいいという選択肢をくれたボスは、そんなに悪者だっただろうか?
六
あのときボスと出会えた幸運を、わたしは一生忘れないだろう。
ボスに出会えていなかったら、わたしの人生は惨めで紙くずみたいなものになっていただろうし、もしかしたら存在そのものを自らの手で消してしまっていたかもしれない。そのくらい不安で絶望していた。自分一人で持ちこたえるのは難しかっただろう。
ボスと出会ったのはエイチ湖だった。どうにかして夜を越せないか思案しているとき、ボスは星を見に来たと話しかけてきた。
「わざわざ星を見に来るなんて、あなた暇なのね」
わたしはカマクラを作ろうと雪玉を転がしていた。暇なのね、という言葉で彼を罵ってやったつもりだった。でもわたしの意図はあまり意味をなさず、彼は「ふむ」なんて、考え込むように腕を組んだ。
そして、
「きみは宇宙についてどのくらい知っているかい?」
とたずねたのだった。
わたしは彼が宇宙について詳しいことをひけらかしたいのだと悟った。さっきの「暇なのね」という発言に釘を刺そうとしているのだ、と。だからわたしは持てる限りの知識を語ってみせた。星の名称、惑星が移動する速度、物質やその成り立ちについて、有名な研究者の名前を羅列して、歴史についてもざっと語った。
ボスはわたしの話を聞いて、「君は頭が良いな」と言った。笑っているようにも見えた。
わたしは急に、身にまとうものがなくなったような錯覚をおぼえて居心地が悪くなってしまった。冷えて感覚のなくなっていたつま先に視線を落とした。
「どうしてポケモンセンターに行かないの」彼はさも不思議そうに言った。
「人に会いたくなかったから」わたしは簡潔に答えた。
「暴力をうけるの」私に訊いている、というよりは、状況を説明するような口調だった。それを今でもよく覚えている。
しもやけよ、と茶化そうとして、やめた。これだけ青黒く腫れていれば誰だって外傷だと気づくだろう。同居人の男は決してわたしを許そうとはしなかった。わたしの身を案じていたわけではない、わたしがいなくなることで男の社会的な信用が下がるからだ。今日はなんとか逃げ切れたけど、この先また捕まってしまうかもしれない未来を想うと惨めになって唇を噛んだ。舌先に鉄の味が広がった。
ボスはわたしを慰めるように、争いの意味について説いた。この世は無駄な争いが多い。新しい平和な世界を創造しよう、と。
「よければ君も、私達と一緒にやろう」
「…………」
そんなことをして、彼になんのメリットがあっただろう。
「君は中々頭が良いみたいだ。そんな君が、こんな扱いを受けていいはずがない」
ただ一つハッキリしていたことは、わたしがこの千載一遇の幸運を逃す手はなかった、ということだけ。
七
ボスが口をすっぱくして言っていた、「争いをしてはならない」という言葉を噛みしめながら、目を閉じて深く息を吸った。彼は今ここにはいないけれど、二人の発端さえ覚えていないような口論は終息に収めなければならないだろう。それがわたしの、大切な仕事のようにも思えた。
「大体、始めから無理だと思ってたのよ」
オフィスの向こうの壁まで届くように、天井を見ながら声を張った。
二人の視線がわたしを捉えた。何を言っているのかわからない、という表情をしている。
「世界を変えるなんて、そんな大層なこと」
さも可笑しそうにあざ笑うと、それがボスのことだと理解したのかマーズの表情がみるみるうちに吊りあがっていった。まるで怒り狂ったギャラドスのよう。
「何言ってんのよ、ジュピター、あんた……」
「だって本当のことでしょ? 現に失敗しちゃったじゃない」
両手を広げて肩をすくめた。
「バカみたいよねえ、自分を神さまかなにかと勘違いしちゃってさあ」
まあわたしは最初から信じちゃいなかったけど、と言い終わらないうちに左頬に小さな電流が走って、首がぐるりと九十度右に回った。マーズの平手が綺麗にわたしの左頬に命中したのだ、わたしが避けなかったから。
サターンが息をのんだ。まばたきの音さえ、聞こえてきそうだった。マーズの目には涙がいっぱいたまっていた。蛍光灯の光を反射して、朱色の瞳が輝いている。
「あんたが信じてなかったからじゃない」「あんたがボスのこと、信じてなかったから失敗しちゃったんじゃない」「全部全部、あんたのせいよ」
マーズは続けざまにそう叫んだ。笛を力任せに吹いたような声にあわせて、目のふちギリギリにたまっていた涙も一緒に流れた。オフィスを後にするその時まで、マーズはわたしを睨んでいた。
「あー……頭が痛い」
静寂を破ったのはサターンだった。
「わたしは頬が痛いわ」
声は弾んで冗談みたいだったけど、痛いのは本当で、左頬は熱を帯びて指先の末端冷え症を際立たせていた。
サターンは大きなため息をついた。
「どういうつもりだよ。あんな、心にもないこと言って」
「……別に。女の醜い争いよ」
サターンはもう一度ため息をついた。疲れたのか、デスクに腰かけて項垂れている。わたしはどこか清々しさを感じていた。彼を守れたことを、左手で実感できたからだろうか。
END
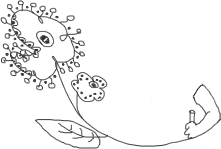
あとがき。
幹部集の中で一番単純な理由で入団したのは、実は木星さんなのでは、という妄想でした。おつ。
タイトルは椎名林檎嬢のシドと白昼夢をお借りしました。
『独り切りじゃ 泣いてばかりになる為
誰かに そっと 寄り掛かるのであろう』
という歌詞の通り、人は誰しも一人ではいられないものなんでしょうね。ギンガ団の人たちもまた同じだったのでは、と思うと、そうせざるを得なかった事情をむりくり彼らに持たせてあげたくなりました。ヨシ子の妄想故、美化しすぎという点はご容赦下さいませ;
ここまで読んでいただけて嬉しいです。お付き合い、ありがとうございました。関東より愛をこめて……ヨシ子。
11/03/18
