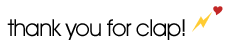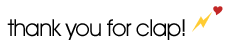|
〜それは仕方ない人間の性〜
飽き性(アカヒカ)
つまんない、をヒカリが連呼している。アカギは机に向かって情報誌(それもテクノロジーとかそういう系)を食い入るように読んでいて、それがさらにヒカリの気を害していた。自分よりも、その堅物な本のほうが面白いのだろうか。
「アカギさん、つまんないです」
アカギは黙って手元にあった本をヒカリの方へ差し出した。アカギの関心が少しでも自分に向いたことを嬉しく思い、ベッドから起き上がって本を受け取ったが、本のタイトルは「何故人類は進化しないのか」という全く興味をひかれないものだったのでぶうたれた。
「やだあ、こんなの読みたくないですよ」
「じゃあ読むな」
「て言うか、つまんないですよアカギさん」
「私はねえ、君を楽しませるために生きているんじゃないんだよ」
「確かにその通りですけどお……」
反論の余地はなかった。せっかくこうして遊びに来たのに、アカギが本ばかり読んでいるのなら意味はない。
ヒカリは荷物をまとめて外に出た。適当に、どこかに遊びに行こうと思っていたのだ。すると後ろから小走りで近づいてくる足音が聞こえて、振り向くとアカギがコートを引っかけて追いかけてきていた。マンションのエントランスで二人はお互いの手を絡めた。
「もう読書はいいんですか?」
「あぁ」
「どこに行くんですか?」
「コンビニに行こうと思うが、君はどこに行こうとしていたんだ?」
「ゲームコーナーで遊んでこようかと」
「……子供があんなところに行くんじゃない」
「どうして?」
「もし何かあったらどうする」
アカギの保護者のような口ぶりがおかしくて、ヒカリは思わず繋いだ手を強く握りしめていた。子供と言いつつも大人の女性と同じ扱いをしてくれる、アカギがどういう風に自分を思っているのかを想像すると、くすぐったくて気持ちがよかった。
END
心配性(アカヒカ←ジュン)
ある日曜日。
ジュンとヒカリはトバリのゲームコーナーでもくもくとスロットのボタンを押していた。五十枚だけコインを買ってそれをどれだけ増やせるか、互いに競い合っているのだ。つまり二人とも暇なのだった。
スロットのリールに例の組織のマークが揃いかけたが右端のマークだけ一段ずれてしまい、下の画面からモンスターボールが消えたことにチッと舌打ちをしたジュンが、
「そういえばお前、まだあのおっさんと会ってんの?」
と訊いた。
「会ってるよ」
「ふーん……」
かなり大きな声を出して会話をしているが、それでもまだ店内の騒がしさのほうが勝っている。ジュンの「ふーん……」というつまらなそうな返事がヒカリに届いたかどうかはわからない。ヒカリはBBタイムに突入していて、ピッピの指示通りボタンを押すのに必死だ。
「おっさん怖くないの?」
「えー?」
「おっさん、怖くないのかって聞いてんの」
「怖くないよー」
ヒカリは笑った。むしろ、なんで怖いの? と。
「怖ぇーじゃん」
「えー、どこがー?」
「顔が怖い。いつも不機嫌な表情してるし。あと何考えてんのかわかんねえとこがあるじゃん」
「なんにも考えてないんじゃないかなあ?」
それはお前だ。
リプレイが揃い再び勢いよく回り始めたリールを睨みながら、その言葉をジュンは飲み込んだ。ジュンは、もうすでにスロットに飽き始めていた。
「何回目?」
爆発しているヒカリの台を覗き込みながら訊くと、ふいに後ろから伸びてきた手がヒカリの肩を捕まえた。驚いて二人同時に振り向くと、例の組織のボス、件のその人が、あきらかに不機嫌な表情で立っていた。
「ここに――なと――だろ」
店内の騒音にかき消され、アカギがなんと言っているのかジュンにはよく聞き取れなかった。でも、どうやらアカギはヒカリに対して憤怒しているようだった。ヒカリはと言えば全く意に反さずに笑っている。
「だってえ、わざマシンが欲しかったんだもん」
「それならコインだけ買えばいいだろう」
今度ははっきりと聞き取れた。落胆したような、安堵したような声だった。
「はーい」
ヒカリは九連チャンしていた台をあっさり離れ、コインケースをバッグにしまった。ジュンにむかって手をあわせ謝罪の意を伝え、口パクで(またね)と言った。もしかしたら(ごめんね)だったかもしれないが、呆気にとられていたジュンにはどちらでもいいことだった。一瞬アカギと目があったが、アカギは何かを恐れるように素早く視線を外しヒカリを連れて行ってしまった。
「何だよソレ……」
苦々しく呟いた。完全に台を離れるタイミングを逃してしまい、仕方なく手元のコインが無くなるまで、ボタンを押す作業は虚しく続くのであった。
END
凝り性(シロナとヒカリ)
激しいバトルだった。チャンピオンと、すでに殿堂入りを果たしている挑戦者のどちらが勝ってもおかしくないという状況ではあったが、軍配は挑戦者にあがった。
「ヒカリちゃん、また強くなったわね」
「シロナさんのおかげです」
「賞金を払わなくっちゃ」
おまもりこばんをつけているポケモンがバトルに出ていたため、シロナは通常支払う金額の倍の金額をヒカリに差し出した。ヒカリは「ありがとうございます」と丁寧に頭を下げて受け取った。子供には大きすぎる額だ、とシロナは少し心配になる。
「ヒカリちゃん、お金の管理はしっかりしているの?」
殿堂入りも手慣れたもので、登録が済む間、二人は手や足をぶらぶらさせながらおしゃべりに興じている。
「はい。大丈夫です」
「そう。あなたはしっかりしているけど、悪い大人もいるんだから気をつけなきゃだめよ」
「わかりました。心配してくれてありがとうございます」
「それにしてもマンムーのふぶきがあんなにあっさり決まるとは思わなかったわ」
「えへへ」
ヒカリは照れたように笑った。
「実はこうかくレンズを持たせてるんです」
「まあ」
シロナは少し考えてから、「確かそれって、ゲームコーナーの景品よね?」と訊いた。
「はい。コインいっぱい買って、交換してもらいました」
「それでお金なくなっちゃったのね」
「あ、でも、もう遊んではいないんですよ。景品に必要なコインだけ買って、交換してもらってるんです」
必死に弁解しているヒカリはまだまだ幼く、シロナは微笑ましい気持ちでいっぱいになる。良いバトルに、可愛いトレーナー。
「よかったら一緒に夕飯でも食べない?」
「あ、ごめんなさい……」
「あら、都合が悪いのね?」
「はい……あの……ちょっと、約束があって……」
マフラーをにぎったり離したり、もじもじしているヒカリの様子で、大体のことを察したシロナは登録の終わったモンスターボールをヒカリに返しながら「じゃあ、また今度ね」と笑った。
「はい、すいません」
「いいのよ謝らなくて。気を付けて帰ってね」
「また連絡します」
「ええ、待ってるわ」
手を振りあって二人は別れた。かつて敵対していた男の元へ、走っていくヒカリをシロナは静かに見送った。振られちゃったわね。一度だけ、そう呟いた。
END
浮気性(デンジ→ヒカリ)
ヒカリはデンジの部屋に遊びに来ていた。
「よっ、ほっ、はっ」
「わー、すごおい」
「まあ実力だな」
デンジの部屋にはゲームコーナーにあるのと同じスロット台が置いてある。ヒカリはかじりつくようにスロット台を見ていた。リールの真ん中には数字の七が三つ、きれいにそろっている。
「どうやってやるんですかあ?」
「練習するんだよ。特訓して、動体視力を鍛える」
「へー。すごいなあデンジさん」
モンスターボールがあらわれる画面は真っ暗で何も映っておらず、リールの回転にあわせて乾いた音楽が鳴っている。デンジはタバコ片手にスリーセブンを止めていく。たまに一列ずれたりもするが、大体の確率で止まり、取り口からは入れたコインが戻ってくる。
「自宅のコンセントに繋がれているスロット台は新鮮ですね」
「そうだな」
「どこで手に入れたんですか? この台」
「拾ったんだよ」
「どこで?」
「ゴミ捨て場」
「ふーん」
ヒカリがコインを手の中でもてあそんでいると、「お前、けっこうゲームコーナー行くと声かけられない?」とデンジが訊いた。ヒカリは首を傾げながら、わかんない、とだけ答えた。デンジはふうんと興味なさそうにタバコをふかした。
「わたしね、ゲームコーナー行くのやめたんです」
含みをもたせて、ヒカリが言った。
「なんで?」
デンジは心底不思議そうに聞いた。世間体を気にする必要がないのなら、自宅の壊れた台よりもゲームコーナーの台で打ったほうが面白いに決まっている。
「行っちゃだめって言うから」
「……誰が?」
「アカギさんが」
ふふふ、とヒカリは笑った。
デンジはタバコを深く吸って小さく肩をすくめた。
「デンジさん、私にもやらせてください」
スロットの乾いた音楽が、この部屋にはよく似合う。
END
〜それは仕方のない人間の性・番外編〜
冷え性(レッドさんとヒカリちゃん)
「ねえ知ってた。ヒカリちゃん」
「何ですか?」
「ゲームコーナーのお金って、誰のものになってると思う?」
「え?」
レッドさんが買い物をしたいと言うので、私はレッドさんにトバリシティを案内していたところだった。
通りの向こうにあるゲームコーナーを見ながら首を傾げる。
あそこのお金とは、ゲームコーナーで購入したときに払うコインのお金のことだろう。
ジュースを飲みながら考える――と、身近なひとの顔が浮かんだ。
まさかという気持ちでレッドさんの顔を見上げたけれど、レッドさんはわたしの考えていることは当たっているよと言わんばかりに笑った。
「……アカギさん?」
「ぴんぽん。大正解」
言われてみれば、確かにそんな気がしてきたけれど。
「そんなこと、考えてもみませんでした……どうしてわかるんですか?」
「あそこのスロットのリールにギンガ団のマークが付いてるんでしょ? だったら多分そうだと思うよ。全額ではないだろうけど、どこの地方も、大人のやることは変わらないね」
「でもでも。アカギさんはもう悪いひとじゃないんですよ」
わかってますよね? という気持ちで、つないでいたレッドさんの手をひいた。
レッドさんは、今度のことは予想できなかったみたいで、一瞬複雑そうな顔をしてみせた。
でもすぐにいつものレッドさんの顔に戻って、「わかってるよ」と言ってつないでいた手を優しく握り返してくれた。
END
掲載期間:2011/04/24〜2012/08/26(2013/12/21)
|